10月30日(水)、第4回松山市栄養教諭中堅研修Ⅰを行いました。
今回は、食🍴に関する指導における実践力の向上を目指し、研究授業と研究協議を行いました。受講者である栄養教諭と学級担任の先生とがティームティーチングで、小学1年生の学級活動の授業を公開してくださいました。1年生の発達段階に合わせ、子どもたちの集中力が持続するように授業の展開を工夫しながら、バランスの良い食事について考えられるようにされていました🥗
子どもたちは授業者の問いかけや友達の言動に、耳👂も目👀も傾けている姿が印象的でした。
研修の機会を提供してくださった会場校のバックアップにもぬくもりを感じる時間でした😊



10月24日(木)、第11回松山市初任者研修を行いました。
まず「特別支援教育の概要」では、愛媛大学附属特別支援学校 校長 樫木 暢子 先生に特別支援教育の基礎・基本をテーマにお話をしていただきました。特別支援学校のカリキュラムや障がい種別の基礎的環境整備、合理的配慮等について詳しく教えていただきました。

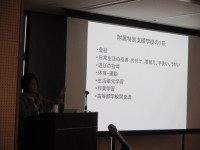

次に、「子どもの特性に応じた支援について」では、本所指導主事が様々な困り感やニーズに応じた支援方法について、ペアやグループで考える場を設け、互いに意見を交流することができました。



午後からは、「教育相談」と題して、愛媛大学教育学部 教授 相模 健人 先生にお話をしていただきました。事例検討をもとに、どんな関わりを持つと教育相談が充実するのか、その具体を体験的に考えることができました。



また、「総合的な学習の時間における探究的な学びについて」では、実際に探究課題を設定し、どうしたら探究のプロセスを進めることができるかについて演習を通して考えました。



受講者からは、
「児童生徒の相談を受ける際、話をただただ聞き取るだけでなく、どのように話を広げ深めていくかについて、視点をいただくことができました。」
「今自分が向き合っている児童一人一人のニーズをキャッチし、支援することができる力を身に付けたいです。」
「一瞬一瞬に熱量を持って児童生徒と向き合い、自分自身がロールモデルになれるよう取り組みたいです。」
まつラボでの学びが、松山市の子どもたちのためになることを願って行った終日の研修でしたが、とても充実した一日となりました✨
紅葉が山を彩る季節となりましたね🍂
令和7年度からは、まつラボで実施する研修への申込や研修評価アンケート等を「全国教員研修プラットフォーム『Plant』」を活用して行うようになります。
そこで、10月22日(火)・23日(水)に、愛媛県総合教育センター 指導主事 藤内 大介 様をお招きして、「全国教員研修プラットフォーム『Plant』フォローアップ講座」を実施しました。
最初に藤内先生より「Plant」の概要をご説明いただき、その後、受講の申込みや管理職の先生の承認作業について、実際の操作を通して確認しました。
新たなシステムの導入ということで、参加者の先生方から個別に質問する様子も見られました。




講座後には、
「操作方法はもちろん、校内の先生方に伝えるべき留意点がよく理解できた」
「他校の先生方と話をすることができ、今後の見通しが持てた」
とお話しされながら、会場を後にされていました。
来年度からの導入に向け、準備が進んでいます!😊
10月23日(水)、大学連携セミナー 第4回国語を開催しました。
今回は、愛媛大学教育学部 講師 清田 朗裕 先生をお招きし、古典教育にスポットを当てたお話をしていただきました。



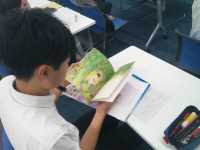
小中の連携はもとより、高等学校の学習内容も見据えた縦のつながりを意識することで、一層の内容充実を図ることができることに気付きました。
「竹取物語」を中心に取り上げ、映像資料も参照しながら、教材化を意図した演習にも挑戦し、楽しみながら考えを深めることができました。
受講者からは、
「まずは、小学校で古典の楽しさをしっかり味わわせ、中学校での学習がより楽しく、充実したものになるように、今回の研修はとても勉強になりました。」
「中学校の先生方ともグループワークができたことで、小学校の指導の在り方を考えたり、『言葉を学ぶ』国語学習の楽しさを感じたりすることができました。」
「今週、校内研修でちょうど『蓬莱の玉の枝』の研究授業を行います。研究授業の前に竹取物語のお話をお聞きすることができたことは、非常に有難かったです。」
といった感想の声が多く届き、充実したセミナーとなりました✨
少しずつ肌寒くなり、秋の気配を感じる季節となりました🌰
10月19日(土)、愛媛大学教育学部 教職ストリート内高度化ゾーンをお借りして、「大学連携セミナー 第4回道徳」を実施しました。
今回のテーマは「よりよい学校生活、集団生活の充実」!
本セミナーは対話を大切にしており、参加者の方から多くの声が🤗
「どんなものが『所属感』をつくってるんだろう?」
「『安心・安全』もポイントになるのだろうか・・・。」
「この教材、難しいなぁ・・・。
自分の生活経験との関わりで考えるのはどうかな?」
今回もとても盛り上がり、内容項目の検討や教材分析を深めるためにも、対話って大切だなぁとしみじみ感じました😌




≪参加者の声≫
🍁自分の学級のことを振り返ることもでき、自分が大切にしたいことを再確認できた。
🍁「よりよい学校生活、集団生活の充実」の価値について、みなさんの意見をたくさん聞いて、考えることができた。今後、その内容項目の授業を行う時に、自分はどのようなゴールを目指して行うのか参考にしたい。
🍁心に残る言葉がたくさんあり、同じ目標であったり経験を共有したりしていくことで、達成感や自己有用感を持つことができ、よりよい集団になっていくのだと思った。また、ネットにおける集団という視点でも考えさせられ、興味深く感じた。
第5回は11月、「ふるさと松山学」教材を活用した大学連携セミナーを予定しています!
みなさまの御参加をお待ちしております😊✨
秋といえば「文化&食欲の秋」😁
10月5日(土)、河原外語観光・製菓専門学校をお借りして、この時期にぴったりな課題別実践力向上セミナーを実施しました。
テーマは「食を通して国際理解 ~専門家に学ぶドイツの伝統料理~」。
講師は昨年度に引き続き、パティシエ・ブランジェ科 エンゲルハート杉沢 多美子 先生とドイツ国家マイスターのエンゲルハート ハインツ ウルリヒ先生です👨🍳
前半は、ドイツの気候や有名な人物、学校、食生活についてのお話です。参加者の先生方は、特に教育制度や松山市姉妹都市 フライブルグの説明に興味津々😲


後半はドイツの収穫祭「オクトーバーフェスト」の食事について学び、全員でマッシュポテトの調理🥔


そして、お楽しみの会食🎵
講師の先生が用意してくださったオクトーバーフェストの定番料理「白ソーセージとプレッツエル🥨」とお肉と野菜がたっぷり入った「グラッシュスープ🥣」もいただきました🍴


会食中にも、エンゲルハート杉沢先生が参加者の先生方の質問に答えてくださり、和気あいあいとした楽しい雰囲気の中で学びが深まっていました。
河原外語観光・製菓専門学校の学生さんも、元気いっぱいにお手伝いしてくれました✨


【受講者の声】
⚫料理をすることだけでなく、その背景にある文化や国民性について知ることで興味・関心が広がり、学ぶことの楽しさや面白さを伝えることができると感じたので、学習でも生かしていきたい。
🔴異文化に触れるという点で、実際にドイツに居住され仕事をされていた方のお話をお聞きして、自分自身の幅が広がったように感じた。また仲間との協働的な学びもでき、和やかで充実した時間を研修をさせていただいた。周囲の人や子どもたちにも異文化交流の大切さを伝えていきたい。素晴らしい出会いと研修をありがとうございました。
🟡「食から異文化を学ぶ」という研修の切り口で、とても興味深く取り組むことができた。早速、家庭でマッシュポテトを作り、家族とドイツの話をしながら食事をした。また、専門学校での研修ということで生徒さん達の学校での様子を知ることができ、子どもたちへの進路指導に生かせそうだと思った。ぜひ、来年度も参加したい。
半日ではありましたが、「知って、体験して、食べてドイツを理解する」という盛りだくさんな研修😆
子どもたちやご家族にも、今回の学びを広げていただけたらと思います😊✨
秋の風が心地よく感じる季節となりました😊
10月9日(水)、昨年度に引き続き、松山市職員と松山市教職員とのコラボ研修を実施しました。今回は女性職員を対象とした研修で、中堅研修対象の中学校教職員も参加しました。対話を通して価値観を広げ、ライフキャリアデザインを描くことを目的とした研修です。
前半は、能力開発システム研究所 木曽 千草 先生による「働く女性のキャリアデザイン」と題した講義・演習です。
後半は、管理職やリーダーとして活躍されている4名のロールモデルをお迎えしてのグループトーク。
最後に研修のまとめとして、様々な対話をもとに考えた「私のキャリアデザイン」を共有しました。




🔶🔶🔶受講者の声🔶🔶🔶
🎤ロールモデルの講師の方から、「小さな『なりたい』『したい』という計画を立てて、叶えてきた」というお話を聞きました。自分はかなり先の漠然とした思いだけだったので、目の前のことにも強い意志を持って向き合いたいと思いました。
🎤日々の小さな目標や自分自身の成長を意識して生活していこうと思いました。様々な職種の方とお話することで新しい考えを広げることもできました。
🎤価値観を柔軟にすることが自分の人生・未来を切り拓くと感じました。今回の研修で、仕事もプライベートも「これだけやったんだから、自分はできる!」と胸を張って言えるだけの努力の裏付けや、自分の気持ちの持ちようであると改めて気付きました。市役所の方に様々な話を聞かせていただき、見聞を広められました。また、様々な観点から自分の人生について真剣に考えて互いにアウトプットしたことで、他の参加者の色々な人生を想像することが面白く、非常に有意義なひと時を過ごせました。
今回のコラボ研修、とても実りの多い研修🌱となったようです。
今後も将来の人生設計をイメージしながら、ご自身の「強み」を生かしていただけたらと思います😊✨
9月28日(土)、課題別実践力向上セミナーを開催しました。今回のテーマは「ふるさと松山学の活用『栗田樗堂と庚申庵』」。
江戸時代に「四国第一の俳人」として全国的に有名だった栗田樗堂について、庚申庵を中心に味酒野を実際に歩きながら学びました。連日厳しい残暑が続いていましたが、この日は🍂秋🍂らしい爽やかな風が吹く、絶好の散策日和となりました🚶


講師は栗田樗堂を長年研究し、庚申庵を次世代に残す活動を続けてこられた、松山東雲女子大学名誉教授 松井 忍 先生です。松井先生のお話を聞きながら、句碑や所縁の地を訪れることで、栗田樗堂の求めた生き方に思いを馳せ、松山の歴史や文化を改めて学ぶことができました。




受講者の感想です。
「大変勉強になり、自分の中でのふるさと松山学における理解が進みました。今後に大いに活かせるすばらしい研修でした。」
「自宅も職場も松山市でありながら、いまだに知らないことがたくさんあると再確認しました。松山市の歴史的で文化的な場所や人物について、さらに学びたいと改めて思いました。そして、松山の良さを子どもたちに語ることのできる教員でありたいと感じました。」
また、「松山なのに旅行に来たみたい!」という声も聞こえてきました。
きっと皆さんのお住いの地域にも、まだまだ知らない「ふるさと松山」の良さがあるはず✨
これからの季節、松山の先人の足跡や歴史、文化を探りにお散歩してみませんか?
 書籍「広がれ! ふるさと松山の心」
書籍「広がれ! ふるさと松山の心」
松山ゆかりの先人78人と伝統文化や歴史のお話17話を掲載しています!
詳しくはこちらへ!
8月1日(木)、第5回中堅研修Ⅱ(教職研修)を行いました。




午前には、愛媛大学大学院地域レジリエンス学環 芝 大輔 准教授より「防災教育の推進」について、また「まなのき」代表 石井 真奈 様より「心理教育“アンガーマネジメント”に基づいた効果的な𠮟り方」についてご指導いただきました。
午後には、株式会社グッドコミュニケーション代表取締役 中田 康晴 様より「業界の変化とキャリア教育の実践」について、また「道徳家の授業づくり」について、学校現場の先生を招いてご指導をいただきました。
どの講義においても、新たな見識を得ることで自分自身を見つめ直し、学校を支える✨ミドルリーダー✨としての資質を高めることができました。
受講者の声を紹介します。
■能登半島地震の事例をもとに分かりやすく説明していただいた。未だに復旧・復興が進んでいない様子を見て、自然災害と人災の両方の側面があると感じた。自然災害が起こることを防ぐことはできないが、事前の準備や事後の復興を予めマネジメントしておくことは可能であると知った。児童生徒を守る立場として、ぜひ実行していきたい。
■学校現場では日々叱る場面は多々ある。感情で叱ることがないように、6秒間待つことや深呼吸をすること、怒りの度合いに点数を付けることなどを実践し冷静に対処していきたい。また、自分は冷静であっても指導上見過ごすことのできないことも多々ある。そんな時は言葉を慎重に選び、児童がよりよい方向に向かうことができるよう指導していきたい。
■人口減少やAIの発展による世界の激変についていくのが精一杯であるが、その延長線上にある子どもたちの進路選択の幅や選択肢も大きく変容してきていることを改めて感じた。自分自身が想像もつかない未知の職種が今後も出てくる可能性もある世の中で、決して変わらない「企業に求められる人材に必要な資質や能力」は、必ず育成していく必要がある。挨拶や礼儀、笑顔…当たり前のことだが、見知らぬ他者に対し、面と向かってできない生徒が増えてきていると感じている。
■道徳科の授業は、自分にとって正直言うと一番苦手である内容である。答えのないもの、生徒への声掛け等、常に自問自答しながら教材に向き合っている。今回の講義では、「道徳的価値」に重点を置いて学ぶことができた。教材によって教科書会社が考える内容項目はもちろんあるが、児童生徒の実態把握をし、その教材からどのような内容項目、どのような道徳的付加価値を見いだすことができるかが、教員の授業準備にかかっていると気づいた。
この研修を生かし、学校のミドルリーダーとしてますますご活躍していただけることを願っています!✨
7月24日(水)、29日(月)、8月2日(金)に、中堅研修Ⅱのうち、教科等指導に係る研修を行いました✨
各教科のプロフェッショナルである愛媛大学の先生や現場の先生方から、具体的な指導法や、各教科で身に付けるべき資質・能力、ICTの効果的な活用法等についてご指導いただきました。






どの講師の先生方も、ご自身の専門教科にこだわりを持っていることがうかがえました。これらの講義のおかげで、受講者は授業力を高めると共に、授業に対する熱意を持つことができました。受講者の声を紹介します。
■国語科において、言葉が持つよさを味わわせるために問いをつくることの大切さを実感した。今回学んだことを元に、授業づくりの在り方を見直し、実践していきたい。また、演習を通して見方・考え方を働かせることとは具体的にどういったことかがよくわかった。
■社会科では、外部人材との連携や、持続可能性を意識した教材開発・単元構成についてお話をしていただいた。外部人材の方と関わることで、地域の一員であることを児童自ら自覚することができるというお話を聞き、コロナ禍で遠ざかっていた地域と学校との距離を、早く元通りにしなければ!と感じた。
■体育科では、得意・不得意や好き・嫌いが顕著に出てしまいがちで、どうすればどの児童も楽しく参加できるかは毎度の課題になっている。愛媛大学 糸岡 夕里 先生がおっしゃった「共生」というキーワードが印象的で、その視点に立って今後目指す体育授業の在り方が見えてきた。
■生活科では、子どもたちがいかに自分と関わり、「〇〇したい」と自分たちで考え、判断し、表現することが大切で、それができた満足感や充実感を味わえることにつながると分かった。今回、グループでセンターの中を探検し、タブレットで写真を撮り、まとめ、友達と伝え合うという活動を通して、生活科においてタブレットを活用するよさを感じた。また、これらの活動を家庭に広げる大切さを改めて認識した。
■音楽科では、器楽分野について全学年を通して見て、実際に演奏することで、内容を構造的に捉えることができた。また、音楽専科の先生との関わりについても教えていただいたので、コミュニケーションを密に取りながら連携していきたい。
暑い中、たくさんの研修お疲れさまでした。夏の研修で得たことを、実際の授業で生かしていただきたいと願っています!😊
残暑の厳しい今秋。しかし、まつラボでは熱い研修が繰り広げられています🍂
9月20日(金)、「大学連携セミナー 第3回道徳」を実施しました!今回は、オンライン💻にて講師のお一人である広島大学 杉田 浩崇 先生にご参加いただき、まつラボに参集してくださった先生方👨👩👧👦とのハイブリッドによる開催となりました。
テーマは「正直、誠実」。
「良心ってどういうこと?」「本音と建前?」「お天道様って何だろう?」
参加者の先生方はこれまでの御経験や学びの中から、様々な議論が飛び交います。オンラインで参加の杉田先生も、まるで会場にいるようにお話されていました。
参加者の先生からは、日頃の授業の悩み事も・・・。
互いに学び合う、残暑に負けない熱い研修となりました😁




第4回は10月の実施を予定しております🎵授業力向上を目指して、共に学びを深めましょう!多くの先生方の御参加をお待ちしております😌✨
9月19日(木)、市内計4校の小中学校を会場に、「第2回松山市3年目研修」を実施しました。
今回の3年目研修は、受講者代表4名による「特別の教科 道徳」と「学級活動」の公開授業及び研究協議です。
授業者の先生方は、教材研究を入念に行い、この日を迎えました。ドキドキの一日だったと思いますが、授業者に立候補し、チャレンジしてくださったその気持ちがとても有り難いです。
研修後の受講者の声をいくつか紹介します。
【小学校 道徳】「授業を参観させていただき、指導者が楽しみながら授業をされている姿勢や、沢山の工夫が授業の深まりにつながっていると感じました。特に、話したり聞いたりすることに児童が集中できるよう、授業の規律を大切にするような言葉掛けや目配りが見られました。」



【中学校 道徳】「普段関わることのない中学校2年生の道徳の授業は、興味深いものでした。発達段階に応じた授業展開になっていましたが、生徒たちは自分の考えを一生懸命まとめていたと感じます。私自身、道徳科の教材研究をするとき「中心発問」に悩まされます。同期の先生方と切磋琢磨しながら、今後もよりよい授業づくりに励みたいと思います。」



【中学校 学級活動(午前)】「中学校の学級活動の授業を見せていただくのは初めてでした。中学生は生徒主体でここまで授業が進められるんだと驚きました。また、ジグソー法を取り入れた活動を初めて見て、子ども一人一人に役割を与えられ、クラスの一員としての自覚をもって授業に参加できるので、自分の実践にも取り入れていこうと思いました。」



【中学校 学級活動(午後)】「話合い活動でのロイロノートの活用について考えることがたくさんありました。共有ノートに打ち込むことで、他の人の意見も参考にできることや、カードの色で意見を瞬時に区別できることなどのメリットがある一方で、子どもたちのつぶやきや会話から生まれることを拾い上げていくことが難しくなるのではないかと感じるところもありました。」



この「3年目研修」は、受講者の先生方にとって「若手教員育成研修」の最終段階という一つの区切りです。これからはミドルリーダーとして若手を育てる側になります。この3年間で学んだことを生かし、「学び続ける教師」の姿勢を忘れずに、自己研鑽に励んでほしいと思います。
今回授業を提供してくださった4名の先生方と会場校の先生方、本当にありがとうございました!
9月20日(金)、さわやかな秋空の下、立岩の地域に元気な歌声が響いています🍂
わくわく出前教室、今回は歌声指導の 塚本 愛 先生の講座が、立岩小学校で開かれました🎵

立岩小学校は、子どもたちの作った俳句をもとに群読コンクールに出場し、昨年度🏆グランプリ🏆に輝いた学校です。
今年の松山市連合音楽会では、その俳句にみんなで曲をつけて演奏するんだそう😲


🔔みんなが大切につくった曲を、上手に歌えるようになりたい!🔔
子どもたちは真剣なまなざしで、先生のアドバイスを聞いていました。
講師の先生の声掛けで、みるみる上手になる様子に、先生方もびっくりしていました。
聞きに来てくれた教頭先生や担任の先生方から、たくさん褒めてもらって、笑顔いっぱい嬉しそうな子どもたち。
本番の演奏が、今からとても楽しみです😊
8月23日(金)、教職員研修大会を実施しました。
教職員研修大会は、先生方に、心身共に健康で、自信と誇りを持って子どもたちの指導にあたっていただくために始まり、学校教育における今日的な課題に視点をあて、教職員としての資質能力の向上を目指して実施しています。
今年度は、関西外国語大学 教授 直山 木綿子(なおやま ゆうこ)先生より「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」について御講演いただきました。
次期学習指導要領の改訂の見通しも踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の実現を支える「個別最適な学び」「協働的な学び」について、丁寧にそのポイントを押さえながら話していただきました。また、「話すこと最高!」をキーワードに、他者の考えを自分の言葉でアウトプットすることなど、研修センター会場とオンラインでつないだ各校の参加者約1700人の先生方と、体感しながら共有しました。




受講者の感想です。
📝今まで漠然と捉えていた「個別最適な学び」について理解を深めることができました。講演の進め方そのものが、これからの授業の在り方を示されていると感じ、2学期以降の子供たちへの関わり方や授業の進め方を考えました。先生がおっしゃられていたように、単元の構成をしっかり捉え、子供が主体的に学ぶ、いい意味で教えない授業を展開していきたいです。そのために、教材研究に力をいれていきたいです。
📝講義全体を通して、「話すこと最強」ということが実感を伴って理解できました。「自分の言葉で言い直す」ことで、学習内容が自分事になるということがよく分かったので、2学期からの授業に生かしていきます。
📝ペットボトルのお茶などのエピソードから、「各教科の見方、考え方」の意味が具体的に分かりました。幅広いものの見方ができる、「こういう見方も面白い」と感じられるような子供を育てていきたいと感じました。今後も、学習指導要領を丁寧に読み込んでいきたいと思いました。
📝直山先生の満面の笑顔と話す力で講演に引き込まれ、あっという間の研修でした。まるで生徒になったような感覚で悩み、発見し、対話をすることができました。「主体的・対話的で深い学び」については、これまでも話を聞いたことはありますが、最後に話されたように「具体」があったからこそしっかりと自分事として考えることができました。
講演を通じて、受講した先生方は、これまでの実践と新たな視点をベストミックスさせて授業改善に取り組むヒントを得られたのではないでしょうか。
2学期からの授業改善に生かしていきたいですね!✨
9月14日(土)、第2回「松山『匠』塾」を行いました。
今回は、愛媛県教育委員会委員や市PTA連合会会長を歴任された髙田 智世 様に講師を務めていただきました。
開会後、髙田さんから早速「3分間で木と実を描きましょう。」というお題が⁉
さらに「四字熟語を書きましょう。」⁉


実はこの2つに演習には仕掛けが・・・🤫
それも踏まえた自己紹介を受講者同士で行い、大爆笑😂
和やかな雰囲気で研修が始まりました!🤗🤗🤗🤗🤗


今回のテーマは「出会い」ということで、受講者にとって「出会い」だと思うものを紙に書き出し、分類しました。
「人」「保護者」「入学式」「スポーツ」「犬」・・・「ホッケ」⁉他にも、「本」や「音楽」「映画」「花」など毎日の生活の中に、たくさんの「出会い」があります。

「人との出会い」においてはコミュニケーションが欠かせません。その際のポイントとして、「てきにちかし」を教えていただきました💕
て・・・てんき
き・・・近況
に・・・ニュース
ち・・・地域
か・・・からだ、けんこう
し・・・仕事、趣味
「何から話せばいいのかな?」という時に話のきっかけになるキーワードです。
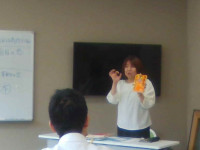
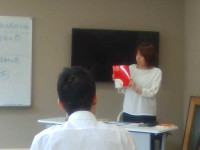
また、髙田先生が出会った本をご紹介いただき、その中から絵本「おこだでませんように」の読み聞かせをしていただきました。
 みなさん、感動でうるうる😭😭😭😭
みなさん、感動でうるうる😭😭😭😭
最後の演習では、「こう」という漢字を受講者でたくさん出し合いました。そのうえで、「聞」いたり「見」たりしたことを基に、「考」え、「行」動を起こし、その際「効」果が出るようにすることで「幸」せにつながる、というお話をしていただきました。受講者が出した、他の「こう」という漢字もつなげられそうです。


あっという間に研修終了の時間⏱
本日も髙田さん、受講者のみなさんとの素敵な「出会い」がありました!✨