令和5年度がもうすぐ終わります。今年度も各種研修や会合等でまつラボを御利用いただきありがとうございました。
このたび、まつラボは4名の職員が異動となりました。在任中はひとかたならぬ御支援を賜り、誠にありがとうございました。
令和6年度も、「つどう つながる つくりだす」をキャッチフレーズに、松山の先生方、そして松山の子どもたちのために充実した取組を行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。


まつラボ西側のトキワマンサクがきれいに咲いています。春ですね。
3月20日(水)秋山兄弟生誕地にて、「秋山眞之生誕156年祭」が開催されました。
献茶や献奏の他、高校総文祭放送部門 ビデオメッセージや全国高等学校弁論大会入賞者による弁論などが行われ、厳かさの中にも瑞々しい雰囲気の中で式典が行われました。

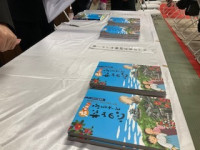
この生誕祭にまつラボ所長、指導主事も参加させていただき、『広がれ!ふるさと松山の心』の書籍販売を行いました。
お声かけいただいた方の中には、
「持っているけど贈答用にしたい」
「自分のふるさとの先人も掲載されているなぁ」
という、あたたかいお言葉をいただきました。
誠にありがとうございました。


ふるさと松山の先人のエピソードを分かりやすくまとめた書籍『広がれ!ふるさと松山の心』。
まつラボでも販売していますが、オンライン販売を始めました!
書籍購入の詳細については、こちらへ!
松山市公式サイト関連ページへ
購入について、お気軽にお問い合わせください😊
3月12日(火)、勝山中学校の3年生に向けて、重藤先生によるおもしろ理科出前教室を実施しました。
もうすぐ中学校を卒業する3年生に、宇宙の成り立ちや元素の起源など、中学校の学習から発展し、高校や大学の学習に繋がっていく内容でした。


「超新星爆発により元素が生まれているんだよ。」
酸素やシリコンのほとんどが超新星爆発で作られているそうです。
そこでできたシリコンでトランジスタや抵抗、コンデンサ、集積回路などが作られ、様々な電気製品が生まれたということです。
人類の進化と星の爆発が関係していたとは・・・😃
「天体=星の学習」と一般的には考えますが、科学の繋がりや奥深さを学ぶことができる出前教室となりました。
3月8日(金)夕方、9日(土)午前、比較的学校を空けやすい時間に、課題別実践力向上セミナー「4月からの授業もこれで安心!タブレット活用 基礎のキソ」と題して、授業でのタブレット活用について研修を行いました。
今回は、タブレットに触れる機会の少ない管理職の先生方や来年度から再任用予定の先生方といった希望者が集まっての研修でしたが、10名ほどの先生方が集まり、「ゆっくり楽しく」学ぶことができました😃🎶


松山市ではすっかり日常的に活用されているロイロノート・スクールの、基本的な機能や授業で使う際の注意など、実際に操作しながら研修を進めました。個別最適な学びには必要不可欠とされるクラウド活用の共有ノートの設定と使用方法や、校務で活用するMicrosoft365のOneDriveの使用方法など、内容が充実していたからか、あっという間の2時間の研修になりました✨


4月の金曜日や土曜日にも同じように参集して体験できる研修を用意しています。今回参加された方からも「もう一度参加したい🌞」と、リーピート参加の声が聞かれました。新年度も先生方をサポートするまつラボの研修、どなたでも参加可能です。ぜひ参加してみませんか?😆
3月6日(水)、城西中学校にておもしろ理科出前教室を行いました。
愛媛大学の佐野 栄先生と大学院生のみなさんによる「大地の変動と岩石の成り立ち」についての出前授業🚗
2学期に小学校で行いましたが、今回は中学生ということで学習内容がより豊富に😁


愛媛県は珍しい岩石がたくさん取れるそうです。
教材の一つである「エクロジャイト」という岩石は日本でも愛媛県でしか採集できない岩石。


時折、「すごーい」「きれーい」という声が聞こえてきます。


タブレット端末でQRコードの資料を見ながら、自分で岩石の勉強をしている生徒もいました✨
岩石の学習がより楽しくなった様子でした😄
今年度、おもしろ理科出前教室は松山市内の21校で実施し、2575名の子どもたちが授業を受けました。
講師の先生方がたくさんの御準備をしていただいたおかげで、理科に興味を持つ子どもが増えたことと思います。講師の先生方、本当にありがとうございました。
来年度も「おもしろ理科出前教室」では、科学の神秘への感動や、科学への興味関心が高まる授業を行いますので、ぜひ御活用ください。
2月9日(金)に開催したセンターフェスタでは、東雲小学校4年生社会科「わたしたちの県の特色ある地いき ー豊かな自然を生かすまち愛南町ー」の授業を行いました。
本単元の最後のまとめとして、3月5日(火)に名古屋市立白鳥小学校との交流会を実施しました👨👩👧👦
白鳥小学校は、明治6年に開校した歴史と伝統のある学校で、学区には熱田神宮、源頼朝誕生の地といわれる誓願寺など、数多くの歴史的遺産があります。
白鳥小学校と東雲小学校の共通点は、郷土の先人「秋山 好古」さん。
今年の交流会では、互いの地域のことを発表しました。
はじめに、白鳥小学校のみなさんが熱田神宮や清水社、白鳥庭園など、校区にある伝統的な建造物、熱田まつり、ひつまぶしなどの郷土の文化について発表しました。
白鳥小学校の子どもたちから発表にまつわるクイズが出題され、東雲小学校の子どもたちも大盛り上がり!


次に、東雲小学校の発表。白鳥小学校と関連のある秋山好古さんの意外な一面について紹介しました。
・・・すると、松山城から「加藤 嘉明」登場!
松山城や松山市の見所として道後温泉や坊ちゃん列車を発表しました。
他にも、社会科での学びの成果を発揮して、砥部町、愛南町、今治市など、様々な愛媛県のすばらしいところを伝えていました。


発表後には質問を行い、さらに交流を深めていました。
両校の子どもたちからは、
🏯愛媛県のことがよく知れた。愛媛県の祭りに行ってみたい。
🏯秋山好古さんの意外なところが知れて、おもしろかった。
🍊互いの学校のことや校区のことをよく分かって、よかった。
🍊愛知県には行ったことがないけれど、今回の交流で身近に感じた。
という感想がありました。
秋山好古さんを通してつながりのある学校の交流会。
交流会終了後、子どもたちはとても満足した表情をしていました。
子どもたちは、共に学ぶ喜びを感じることができたのではないでしょうか✨
2月27日(火)、東雲小学校4年生社会科「わたしたちの県の特色ある地いき ー豊かな自然を生かすまち愛南町ー」の授業を紹介します。
2月9日(金)に開催したセンターフェスタでは、この単元の導入第1時の授業を公開しましたが、子どもたちの充実した学びは続いています。
公開授業は、学びの選択肢として愛南町の様々な資料をクラウドで共有しながら情報収集し、「学び合う学習」を目指すものでした。この授業で「愛南町について知りたい」という気持ちを高めた子どもたちは、自分でテーマを決めて愛南町のまちづくりについて調べ学習をしてきました😊


この日は、愛南町役場の方とオンラインでつなぎ、愛南町の特色やまちづくりについてお話を伺い、質問や感想を伝えるなど双方向の交流をしました。調べただけでは分からない、実際にまちづくりに携わっている方の思いや願いを聞いて、より実感を伴った理解につながっているようでした😉👍


そして、本単元の最後の時間には、「愛媛県ガイドキッズ」として東雲小学校と交流している名古屋市の白鳥小学校との交流で学んだことを伝え合います。
「センターフェスタの授業が、今までで一番楽しかったです!またしたいです!」と授業者の先生が言ってくださったことが、何よりうれしいことでした。
公開することでいただけた助言も生かしながら、子どもの学びも、私たち教員の学びも、続いていきます✨
センターフェスタ後に、センターに届いた貴重な御意見・御感想を紹介します✨
基調提案について
全国学力・学習状況調査の分析結果等、様々なデータを根拠として、これまで授業改善に取り組んできた成果と課題が具体的に示された。これまでは松山の授業モデルを実践することに重きを置いていたが「学び合う学習」についてのイメージが鮮明に変わった。小集団で意見を交わすだけでは不十分であり、他者と協働しながら主体的に学習に取り組む学習へ進める必要性を感じた。公開授業の参観でも、資料を見ながら、課題意識を持って参観することができた。
特別授業・公開授業について
子どもたちが既習事項や自分の知識から考えたことを、積極的に伝えようとしている姿が非常に印象的でした。また、先生が「答えは○○である」「実際は△△だ」などと教え込むのではなく、子どもたちの意見を一通り聞いた上で、「先生はこんな風に考えてみたよ。少し聞いてくれる?」のように、子どもたちと同じ目線でお話しされており、勉強になりました。また、普段の授業における自分の言動について振り返るよい機会となりました。
いろいろな個性を持った子どもたちが、自分のペースで、目標達成のために頑張れる工夫が散りばめられている授業だと思った。また、授業の中で一人一人が役割を持って活動に取り組むことで、仲間と協力して最後までやり遂げた実感が持てるのだろうと感じた。
研究協議について
教師主導の一斉授業ではなく、いろいろな資料を基に取捨選択をしながら、子供たちが自分の調べたいことを決め、調べ学習を進めていくという単元構想に興味を持った。調べ学習を進める中で、必要な知識を知ったり友達と関わったりすることで身に付けた知識や技能は、一斉授業以上に子どもたちに定着すると考える。
講演について
まさに「教える授業」から「学び合う学習」へ発想の転換を図る講演内容であったと思います。近くの先生と一緒にお話をしながら、「学び合う学習」の面白さ、楽しさを実感することができました。
フェスタ全体について
今年度、初めてフェスタに参加させていただきました。フェスタと呼ぶにふさわしい活気があり、公開授業、分科会、講演、どれをとっても「今、学びたい」旬の内容が盛りだくさんだったと思います。
2月28日(水)、令和5年度最後の「わくわく出前教室」を実施しました。
元小学校校長 乘松 秀樹 先生が、垣生小学校6年生に向けて「国際理解」に関する出前教室を行いました👨👩👧👦
垣生小6年生は、社会科の学習や総合的な学習の時間に、様々な国や平和学習について勉強しているそうです。
本日のテーマは「マレーシア」について!
乘松先生はマレーシアの日本人学校に勤務されていたため、御自身がマレーシアで生活した体験をもとに、マレーシアの「自然」「人」「文化」「食べ物」などについてお話されました。
乘松先生が日本と比較しながらお話していたため、子どもたちは驚きが隠せません!
「マレーシアの学校で、サソリが出たよ」→「えー😲」→「垣生小には出ないよね」→「うんうん」
「日本には四季があるけど、マレーシアは一年中夏で、気温が35度!」→「えー😅」
「1ヶ月、断食っていうのがあるよ」→「え?何も食べれないの😫?」→「日が出てない時間は食べていいんだって」→「なるほど〜😌」
「日本と似てるところもあるよ」→「あ!凧!こま😆!」


乘松先生は、マレーシアでの戦争についてもお話されました。
これまで驚きを隠せずに口々に話していた子どもたちが、真剣な表情に!
乘松先生から「マレーシアにはいろいろな人種の人が生活していて、違いもいっぱいある。違いがあっても、マレーシアの人たちは違いを認め合って生きている。違いがあるのは当たり前。自分たちも真似して、違いがあってもケンカをせずに生活したいね。」という大切なお話をしてくださいました。
今日のお話を聞いて、子どもたちは持続可能な社会の実現を目指して考えを深めていってくれるでしょう😌✨
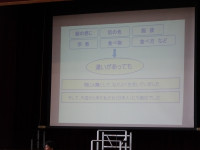

令和5年度の「わくわく出前教室」は、今回が最終回となりました。
なんと!4500人を超える子どもたちが「わくわく出前教室」に参加しました😲
そして、子どもたちはもちろん😊
学校の先生方も講師の先生方も、「わくわく」が止まらない出前教室ばかりでした!
来年度は、どのような「わくわく」と出会えるのでしょうか?!
乞う御期待~🎵